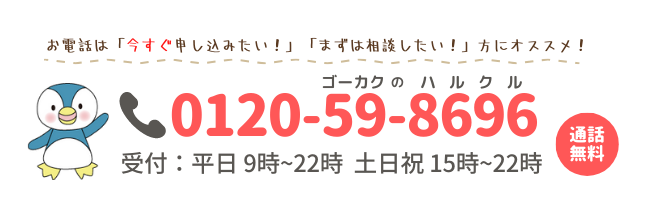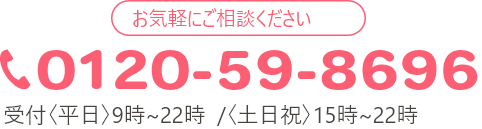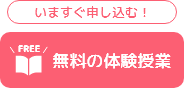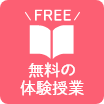こんにちは!勉強が苦手な子専門の家庭教師のえーるです。
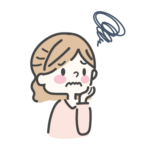
うちの子、最近学校を休みがちです。不登校と家庭環境は関係ありますか?
不登校の原因は、お子さんによってさまざまですが、家庭環境も要因の一つです。
子供の成長に応じて親へのイメージは変わっていきますが、子供が幼ければ幼いほど、親はなんでもできる魔法使いのような存在です。
そのため家庭は安心感で包まれていることが望ましいです。しかし、不登校になりやすい家庭の場合、子供が安らげる環境ではないことがあります。
今回は、不登校になりやすい家庭の5つのタイプと、不登校になりやすい家庭が変わる3つの改善方法について解説していきます。
お母さんの悩みが少しでも軽くなってもらえたら嬉しいです。
私たち、家庭教師えーるは、26年間の指導の中で11,183人の小・中・高校生の生徒さんに勉強のやり方を指導してきましたまた、勉強が苦手なお子さん、不登校や学習障害を持つお子さんのご相談も無料で受け付けています。「うちの子、大丈夫かな?」 そんな不安があれば、どうぞお気軽にご相談ください。お子さんの「勉強の悩み」に、私たちが寄り添います。
不登校になりやすい家庭の5つのタイプ

子供が不登校になりやすい家庭は、5つのタイプに分けることができます。
長崎県立子ども医療福祉センター小児心療科の小柳先生は、第65回日本小児保健協会学術集会のシンポジウムで「子供が不登校になる要因にはさまざまなものがあるが、そこには家庭の養育環境が大きく関わっていることも多い」と述べているように、不登校になりやすい家庭は少なからず存在しています。
ここからは、不登校になりやすい家庭の5つのタイプについてご紹介いたします。
①子供に対して無関心な家庭
子供との接し方に悩む保護者の方は少なくありませんが、子供との関係が希薄だと、子供は保護者に対して「相談する」という選択ができなくなるので、不登校に繋がる場合があります。
また、両親ともに子供に対して関心があまりないというケースの他に、お母さん、お父さんのどちらかが子供に対して関心が無いというケースは非常に多いです。
例えば、育児や家事は母親に任せきりで父親は仕事のみを行い、家に帰ってもスマホ片手に食事をして会話はほとんどナシ。子供も空気を感じ取り、話しかけなくなってしまいます。

母親、父親の両方との関係や、家庭での生活の中で子供が学べることは多く、本来家庭は、社会に出る前の学校のようなもの。つまり、子供が人との関わり方を学ぶ重要な場なのです。
そんな家庭内で、どちらか片方が子供に対して関心を寄せていないということは、社会適応力の欠如に繋がり学校でも上手くいかなくなり不登校に繋がってしまうことがあります。
また、子供に関心があるとはいえ、その関心が勉強面や成績だけに偏ってしまうのもよくありません。「成績が悪い=ダメな子供」という評価基準になり、子供は成績しかみていないと感じ、親のことが信頼できなくなる可能性があります。
勉強や成績のことだけでなく、子供の全体をみてバランスよく関心を寄せて接してあげることが大切です。
②子供に対して過保護な家庭
子供に対して関心を寄せていない無関心な家庭が、不登校の原因になっているというお話をしましたが、一方で子供に対して関心を寄せすぎてしまっている過保護な家庭も、また不登校の原因になってしまうことがあります。
それなのに「〇〇しようね」「○○がいいわ」と、子供自身が考える前に保護者が決めてしまったり、先周りしすぎると子供は自分で考えることができなくなります。
そうなると、学校生活で自分で考えて行動しなければならないシーンで何もできず、周囲から低い評価を受けてしまいます。
過保護は、子供が自分で考えて、行動して、失敗し、それを繰り返しながら成長していく機会を奪い、自己肯定感が下がりやすくなり、自信のない子に育ってしまう可能性があります。
このように過保護な家庭もまた、不登校になりやすい家庭となっています。
③過剰な教育熱心や躾が厳しすぎる家庭
子供への期待値が高く、良い学校を出て良い会社に就職してもらいたいという思いから、勉強のことでついつい口うるさくなってしまう親御さんも多いかと思います。もちろん教育に力を入れるのはお子さんの将来のためでもあり、決して悪いことではありません。
ですが、それが子供のキャパシティーを超えていたり、期待が大きすぎるあまり精神的負担になっていることもあります。特に幼い頃から受験に向け、遊ぶ時間を削り毎日塾へ通ったり、勉強漬けになっているお子さんは注意が必要かもしれません。
ある日突然我慢が限界に達して爆発したり、反動から学校に行かなくなる、勉強を一切しなくなるケースって多いんです。実際、私達えーるには中学受験を終えて燃え尽き症候群になり、せっかく合格したのに中学入学後から不登校になったご家庭からのご相談が沢山寄せられます。「この子は公立でのびのびさせた方が良かった…」「親がムリさせて可哀そうなことした…」と振り返って、過度な勉強させたことを後悔されているお母さんも少なくありません。
また、親の躾が厳しすぎて不登校になるケースもあります。子供の気持ちを一切聞かず「あれはダメ」「これはダメ」「こうしなさい」「あーしなさい」 一方的に親が制限をかけるのも危険です。素直に聞いているようで毎日窮屈でストレスいっぱいになり、親への反発心で不登校という形で表現する子もいるんです。お子さんの意思を尊重しながら、その子に見合った教育や躾をしてあげましょう。
④両親の仲が悪い家庭
子供の世界は、「家庭」と「学校」の2つでできていると言っても過言ではありません。
50%は家庭、残りの50%は学校の割合で子供の世界ができていると仮定した場合、もし家庭で両親の仲が悪く、毎日のように喧嘩が絶えない家庭であったのなら、子供の世界の50%は殺伐とした世界ということになります。
家庭内における両親の不仲は、大人が想像する以上に子供は大きなストレスを受けているものなんです。大人であれば、学校と家庭以外に幅広い世界を知っているので、仮に「家庭」という世界が殺伐としていても、「他の世界は素晴らしいから人生を諦める必要はない」と気持ちを切り替えて乗りこえることができるでしょう。
しかし前述したように、多くの子供の世界は「家庭」と「学校」の2つのみです。
子供は知識も経験もまだ少なく、思考も大人のようにできないうえに、自由に過ごすことができるわけでもなく制限的です。
そう考えると、家庭で両親の仲が悪いというのは、子供にとって絶望的なことであり、人生を諦めるのに十分すぎる理由になることから、不登校に繋がってしまう可能性があります。
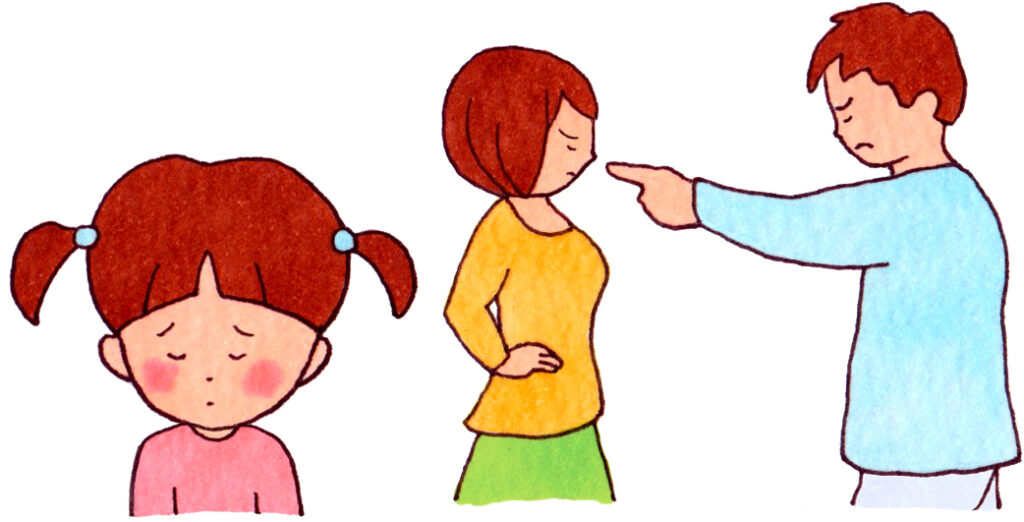
お子さんに安心して学校生活を送ってもらうためにも、両親の関係は良くなければいけません。
⑤劇的な環境変化があった家庭
子供との距離感が程良く、両親の仲も悪くはない。このような家庭であっても、子供が不登校になることがあります。
例えば、家庭の事情で両親が離婚した、あるいは家族の死別、全く知らない土地に引っ越したなど、誰にでも起こりうる劇的な家庭環境の変化は、子供にとってこれまでにない程の壮絶なストレスになります。
特に両親の離婚は現代では珍しくなく、厚生労働省の調査(※)によると令和5年度では18万3808組の夫婦が離婚しています。
親が離婚した子供の気持ちは、両親の離婚を経験した子供にしか分かりません。
親が離婚することで、「これからどうなるの?」「将来はどうなるの?」「もう学校の友達とは会えないの?」 など、その子にしか分からない気持ちの変化を、大人が「なんとなくでも、そのうち分かってくれるだろう」と思うのは傲慢と言えるでしょう。
特に、少しの変化にも敏感な年頃である思春期の子供ほど、両親の離婚は大きく影響を受けてしまいます。両親の離婚は、子供の不登校の原因になるには十分すぎるくらいショックな出来事と言えます。
(※)労働省HP人口動態統計月報年計(概数)の概況 gaikyouR5.pdf (mhlw.go.jp)参照
不登校になりやすい家庭はどうするべき?3つの改善方法
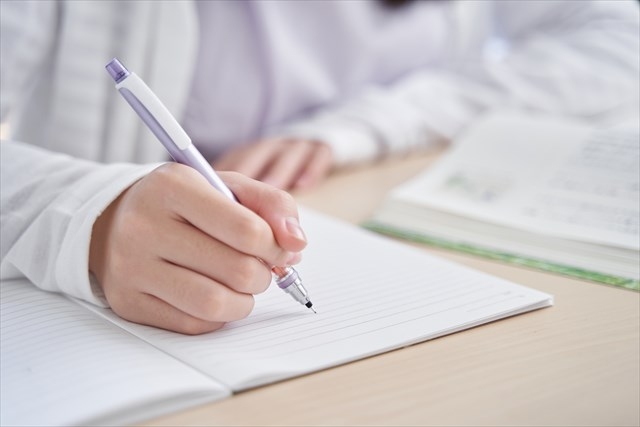
子供が不登校になった家庭は、なんとかして子供を学校に通わせようと奮闘することでしょう。
しかし、根本的に不登校になりやすい家庭そのものが変わらなければ、半日あるいは1日だけ学校に行けたとしても、子供は再び不登校になってしまいます。
不登校は子供のSOS。不登校になりやすい家庭は、これからどうやって変わっていけばいいのでしょうか?
①子供にとって家庭が落ち着けるようにする
ここまで、子供の世界は「家庭」と「学校」の2つでできているとお話ししました。
50%が学校、50%家庭なので、半分の割合を占める家庭が子、供にとって落ち着ける環境にすることは必須です。そのためには、まず「私がこの子だったら」と考えてみてください。
どういう家庭だったら、どういう声かけをしてくれたら、どう接してくれたら、この子はこの家に安心して居られるのか考えてみましょう。
親子の関係も良好で家での居心地も良ければ、お子さんは安心して学校に行くことができるはずです。
②雑談ができる親子関係を築く
人と人との関わり方を学ぶためにも、親子間の雑談は非常に重要と言えるでしょう。
雑談は「何も考えずに雑な談話を楽しめる会話」だからこそ、深く思考を働かせなくても、気持ちを楽にして話すことができ、親子のコミュニケーションに最適です。
雑談では、ぜひ子供が何を感じて、何を思っているのかを注目して、子供の話しに共感してあげてください。
共感は会話する人に対して安心感を生み出し、会話そのものが楽しければ、再びこの人と会話をしたいと思うことができるようになります。
例えば、夕食の時間の会話を大切にしたり、普段各々がスマホを見る時間を減らし、家族団らんの時間を作り、その日にあった出来事を親子で共有します。お子さんの話し耳を傾け、「ちゃんと聞いてるよ」という姿勢を見せることで、お子さんは安心して何でも話してくれるはずです。
良好な親子関係を築くためにも、ぜひ親子で雑談を楽しんでみましょう。
③成功体験を積む
家庭環境の改善、親子関係の改善がある程度できてきたら、子供自身に成功体験を経験してもらいましょう。
成功体験とは、簡単に説明すると「できた!」という経験のことです。成功体験は自信に繋がり、興味関心を寄せることに対して「やってみよう」という気持ちを育む重要な燃料として欠かせません。
特に、勉強は一度躓いてしまうと、雪だるま式にどんどんわからなくなっていきやる気も低下します。先生と子供の二人三脚で「できない」を「できる!」に変えて成功体験を積ませていきましょう。
まとめ
不登校になりやすい家庭には5つのタイプが存在しており、子供にとって家庭がどれだけ重要な環境かがわかります。
不登校になりやすい家庭は、家庭環境の改善、親子関係の改善、そして子供が成功体験を積むことで、再び学校に通うための準備をすることができます。
現代は学び方・働き方の多様化が認められつつある時代になってきているので、「学校に行けなければ将来が不安」と悲観することはありません。
子供は可能性の塊です。
親子間だけで悩まず第三者や専門機関などを通して、少しずつ前に進んでいきましょう。


不登校の子には「無理なく少しずつ」が重要

ここまで読んでくださり、ありがとうございます!家庭教師のえーる代表の坪井です。
不登校は、お子さんだけでなく保護者さんもとてもおつらいですよね。
私たちは、関西の小中高校生を対象に26年で11,183人のお子さんの勉強に関するお悩みを解決してきました。不登校で悩んでいるお子さん・お母さんの力になれるよう、全力でサポートいたします。
もし、お子さんが不登校で「どうすればいいのかわからない」という不安をお持ちの方は、小さなことでもかまいませんので、一度えーるにご相談ください。もちろん相談だけになっても構いません。
\ 【関西限定】地元密着26年!家庭教師のえーる /